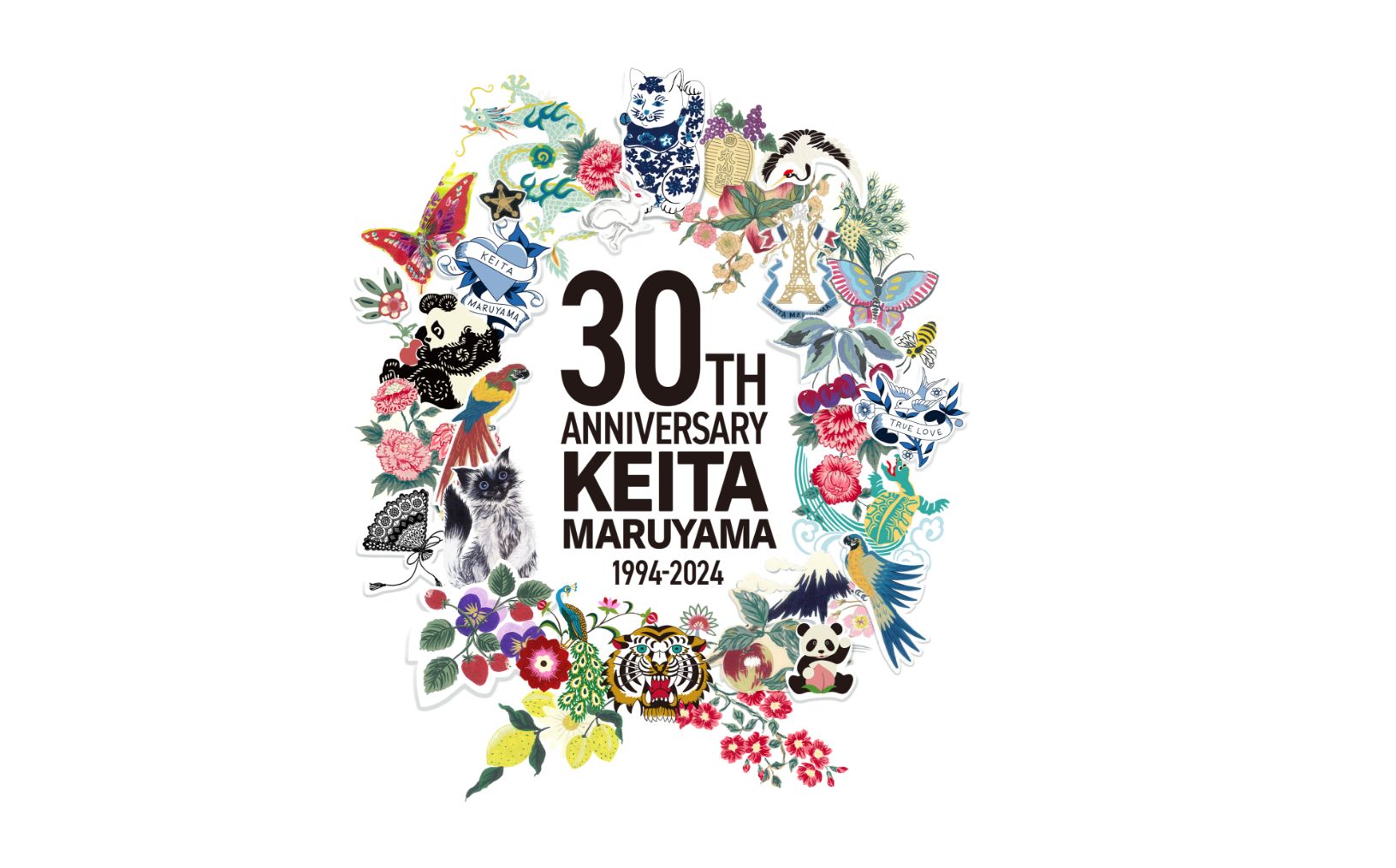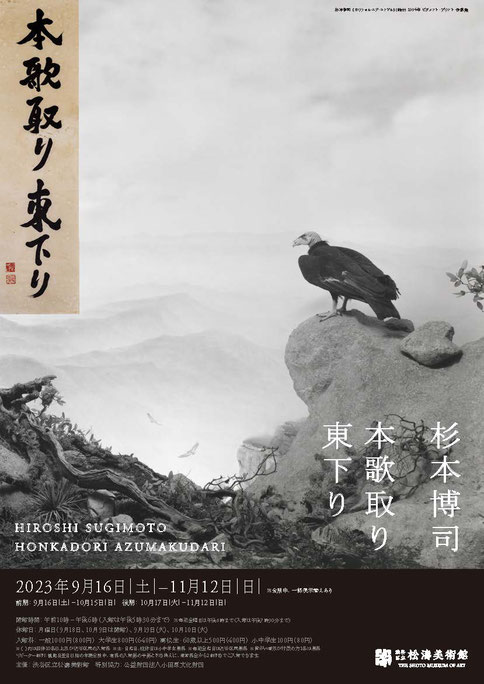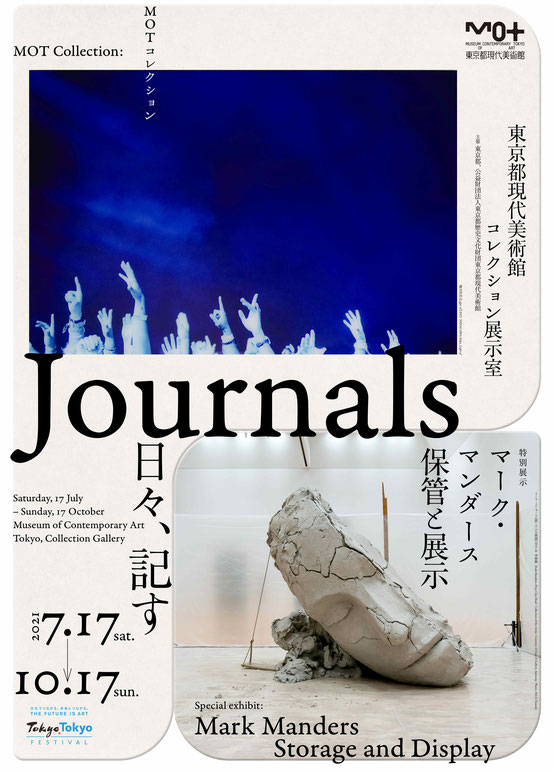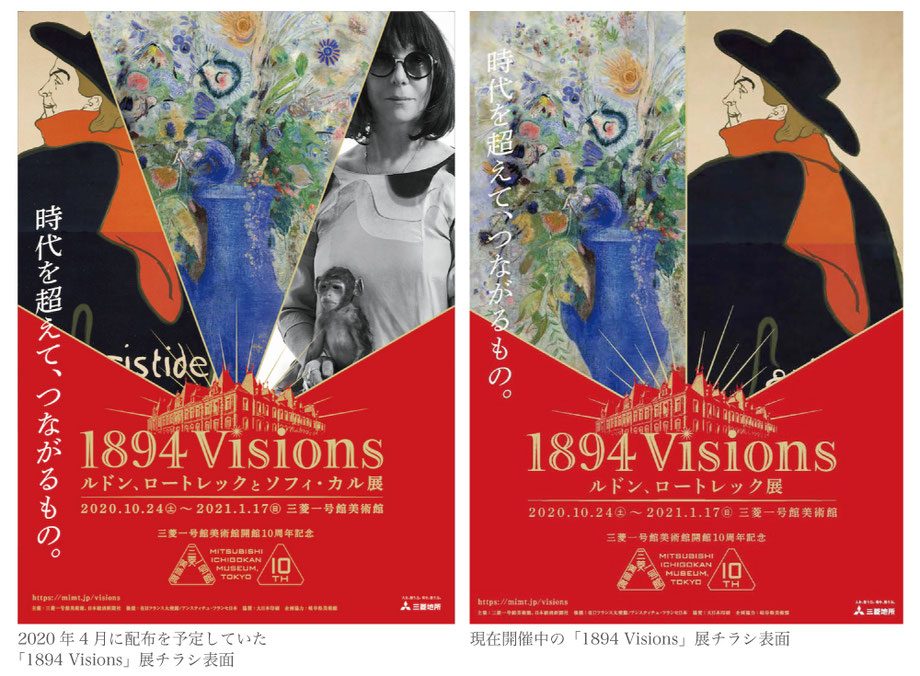この光景は以前どこかで見たように思う、街から人影が消え、人々が疫病の恐怖に慄き、不気味に静まり返っている。そうだその記憶は私の記憶ではなく人類の記憶だ。あのヨーロッパの人口の1/3ほどが失われたとされるペストの大流行だ。パンデミックという言葉もその時生まれた。その爆発的な流行は14世紀からはじまり断続的に17世紀まで続いた。私はその記憶の断片を写真に撮ったことがある。かつてロンドンの蝋人形館マダム・タッソーには「恐怖の部屋」と呼ばれる部屋があった。その中にプラーグと題されたペスト流行中のロンドンが再現されていたのだ。私はヘンリー8世やエリザベス女王を撮影する傍ら、この恐怖の館の撮影に挑んだのだが、この展示は今はない。ポリティカルコレクトネスが叫ばれてから撤去されてしまったのだ。しかしその記憶が600年後もこうして生々しく伝えられたこと、私はそのインパクトの強さに慄いたのだ。
今その写真を見返してみると医者が防護マスクを着けて死者達に香の煙を振りまいている。治療法などなかった時代、死者への魂の救済の儀式さえ覚束なかったのだ。屍体は大八車に山積みにされ、その車を引く俥夫も感染しているらしく息も絶え絶えだ。興味深いのはこの医者の着ける防護マスクは顔全面を特殊なメガネと籐製の覆いで作られていて、その形状は今の医療用マスクとそっくりなのだ。
しかし世の中は悪いことばかりでは無い、1666年ロンドンのケンブリッジ大学は封鎖され、学位を取ったばかりのアイザック・ニュートンは疫病感染を避けてイギリス東部の故郷、ウールスソープで1年半を過ごしたのだ。この間にニュートンは生涯に成し遂げた重要な研究成果の着想のほとんどを得た。万有引力の発見、微分積分法、光学理論の研究、あの有名なリンゴが木から落ちるのを見たのもこの場所だ。ニュートンは自宅二階にプリズムを置き、暗くした部屋に太陽光を導き入れて、白光と思われていた太陽光が7色に分光できることを発見したのだ。この硝子を使った光の研究は後の19世紀の写真の発明へと連なっていく。私は今を生きる写真家として、この初期の実験を再体験してみたいと思い、2004年の冬、自宅に硝子のプリズムを磨き設置した。私は冬の澄み渡った大気に昇る陽光から分光される目眩く輝く色の帯の中にいて、恍惚感に溺れながらカメラを手にその光の色の中に入っていった。私は形を写すのではなく色そのものを撮りたかったのだ。単純なものほど難しいことを私は思い知らされた。15年に渡る研究の結果ようやく満足のいけるプリントが完成した。この作品は写真というよりも絵画に近い、マーク・ロスコが絵の具で表現しようとしたことを、私は光そのもので表現したいと願った。絵の具は物質だ、私は絵の具という物質を介さないで、光の色そのものを定着したいと夢想したのだ。今年、世界への初公開は、京都市京セラ美術館のリニューアルオープン、「杉本博司 瑠璃の浄土」展で発表される予定だった。しかし今美術館は封鎖され、美しく仕上がった展示は誰の目にも触れることなく静かに佇んでいる。カタログだけは刷り上がって買うことができるのがせめてもの慰めなのだが、私はニュートンの疫病時代の因縁といったものさえ感じるのだ。
私はアーティストとして、文明の行く末をテーマに多くの展覧会を催してきた。そして今年の「瑠璃の浄土」展で私は日本人の死生観、日本人がどのように死後の世界を観想してきたのかを、アーティストとして反芻してみた。いわば仮想の御寺を今の世に荘厳してみたのだ。しかしその門は閉ざされ、死後の世界はより現実味をおびて世界を席巻しているという皮肉に私は言葉を失う。
中世のペスト流行、人々は神が人を罰しているのだと思った。しかし今、神は人を罰するほどの力を失ってしまった。私は自然の摂理が人を罰しているのではないかと思うのだ。文明とは環境破壊を食い物にして成長する。今、成長の臨界に達した一生命種としての人類は、全滅を避けるための自動調節機能が働いて、活動の自粛を求められているのだ。全世界が自粛する中、ベニスの運河には透き通った水が戻り、京都やフィレンツエには昔日の面影が戻ってきた。これからの世界の行く末、私は成長しないことこそが成長であるという文明の転回点に今我々はいるのだと思う。1962年に文明の行く末に警鐘を鳴らしたレイチェル・カーソンによる名著「沈黙の春」。農薬や化学物質の汚染によって近い将来、春に鳥が鳴くことがなくなるという恐ろしい予言だ。今年の春、幸いにも鳥はまだ鳴いている、しかし世界は沈黙の中に静まり返っている。
出典:読売新聞 2020年4月15日朝刊